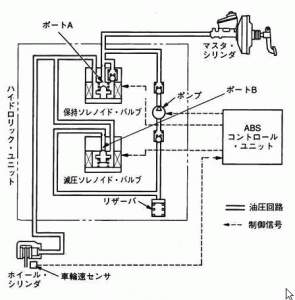問題
ブレーキに関する記述として、不適切なものは次のうちどれか。
①ブレーキは、自動車の熱エネルギを運動エネルギに変える装置である。
②停止距離とは、危険知覚後、運転者がアクセル・ペダルから足を離したときから車両が停止するまでに走行した距離をいう。
③ブレーキ液は、走行期間が増すにつれて、含まれる水分が増加する性質がある。
④制動距離とは、ブレーキが作用して減速し始めてから車両が停止するまでに走行した距離をいう。
解説
停止距離=空走距離+制動距離
空走距離は危険知覚後、運転者がアクセル・ペダルから足を離したときからブレーキが作用をはじめるまでの走行距離。
制動距離とはブレーキが作用して減速し始めてから車両が停止するまでの走行距離。
だから②、④は正しい文章である。
③ブレーキ液は圧力を掛けたり、圧力が抜けたりするたびまた、温度が上昇したり、下降したりすることによって空気中の水分を吸収していく。
だから③も正しい文章である。
水分を多く含んでしまうとベーパーロックを起こしてしまうのでとても危険です。
ブレーキ液は定期的に交換する必要があります。
①は「ブレーキは、自動車の運動エネルギーを熱エネルギーに変える装置である。」
で正しい文章に変わる。
解答 ①